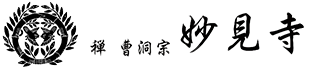-
剪定
2015年01月27日
一月の末になってしまいましたが、皆様新年明けましておめでとうございます。
近況報告もあっという間に3年目を突入いたしました。少しずつではございますが、妙見寺の活動・曹洞宗の活動を知っていただけているのではないでしょうか。このHPは全て副住職自ら更新しておりますので、多少見づらいところはございますが、愛情込めて更新をさせていただいております。いつも見ていただいている方、たまに見ていただいている方、本当にありがとうございます。温かく見守っていただければ幸いでございます。
さて、今月は住職と共に境内の剪定を行っております。全体を見ていただきたかったので、かなり見づらいですが写真の真ん中で、住職がハシゴ使って木に登り、伸びすぎた枝や葉っぱを落としております。
曹洞宗は「生活の全てが修行」と道元様はおっしゃられましたので、この剪定にも意味があり、学びがあるのです。今回一つの学びがありました。
それは、「とても危ない」ということ。(笑)
智慧の仏教ですから、できるかぎりケガのないよう工夫をして作業してまいりたいと思います。合掌。
-
師走
2014年12月22日
今朝は太子町も少し雪の降る寒い朝となりました。皆様如何お過ごしでしょうか?
お寺の周辺は日中になると太陽が出てまいりましたのですぐ解けましたが、毎年雪が積もり、雪かきに追われる地域の皆様には頭が上がりません。今月は境内の墓地予定地の測量、並びに設計を行っております。墓地をお待ちの方には大変ご迷惑をお掛け致しております。
来月中には許可が下り、墓地予定地の造成工事が始まる予定となっております。合掌。

-
裏をみせ表をみせて散るもみじ
2014年11月27日
11月の大阪は、雨も無く平年より温かい日が続きましたね。過ごしやすい日が多く、紅葉を見に行かれた方も多いのではないでしょうか?
妙見寺にあるモミジも、なんとか見頃を迎えました。京都・嵐山のようにとても色鮮やかとはいきませんが、きれいな赤色です。朝日に照らされ二上山をバックに見る紅葉はとても穏やかな気持ちになります。今回は少し長文になりますが、有名な詩のお話をさせていただきます。
裏をみせ表をみせて散るもみじ
これは曹洞宗の僧侶である良寛様が、谷木因(たに・ぼくいん)が詠んだ「裏ちりつ 表を散つ 紅葉なり」という詩を簡単に作りなおした詩です。
良寛様は亡くなる直前に弟子である貞心尼(ていしんに)に、この詩を詠んだといわれております。ひらひらと裏も表も見せて散っていく紅葉をご自身にたとえ、「私はあなたに人間としての表も裏も、すべてをさらけ出し、あなたを受け入れてきた。私も紅葉のように安心して仏様の浄土へ還っていくよ」とこの詩に表と裏とが出てきますが、人間の感情にも長所と短所があります。人は関わり合いの中で、その人の良い部分を見ている時には、あの人は素敵な人だから一緒にいたいなという感情になります。しかし時に悪い部分が見えた瞬間、この人と私は合わない、あまり関わらないようにしようという感情が生まれてしまいます。
人は自分に都合の良いものは受け入れ、悪いものは遠ざけようとするものです。生と死もそうです。生きることに執着をし、死を遠ざけて考えるのが私たち人間です。しかし諸行無常(変化しつづける世の中)ですから、必ず「生」には「死」があり、「自分」には「他人」があり、「楽」には「苦」があり、すべては相対的な関係があるわけです。
そのような世の中であるからこそ良寛様は、相手を受け入れ、自分の死をも受け入れることの大切さをこの詩に表されたと思います。
全てを受け入れて生きていくことは、自分の都合ばかりで生きていてはダメだということです。相手の気持ちに寄り添い相手の短所も受け入れ、許すということ。死が必ずあるということを受け入れるからこそ、一日一日を大切にし感謝をして生きるということ。
ひらひら落ちていく紅葉の葉に良寛様の想いを感じ、じっくりと人生を生きていきましょう。合掌。

-
恒例の坐禅会。
2014年10月21日
先週土曜日、10月恒例の竹内灯路祭りが開催されました。毎年雨に見舞われていた灯路祭りも、今年はとても快晴に近い晴れ模様。10月前半はスーパー台風発生の為、灯路祭りへの被害が懸念されておりましたが、太子町はなんとか被害なく灯路祭りの日を迎えることができました。
妙見寺でも坐禅会を開催させていただき、坐禅初挑戦の方、一度経験のある方と、大体半々の割合での坐禅会となりました。昨年参加された方もお越しくださり、大変嬉しい限りでございます。「坐蒲(ざふ)」と言う黒くて丸い座布団で坐禅される方、イスで坐禅をされる方、皆様には無理なく、坐りたい足の組み方で坐禅していただきました。坐禅終了後はお茶を飲んでいただき、皆様と楽しく歓談させていただきました。ご遠方からお越しの方も多く、皆様と貴重な20分間を過ごすことができました。まだ坐禅をされたことがない方、是非お寺で一度坐禅をしてみてはいかがでしょうか。合掌。


-
支援活動。
2014年08月24日
台風の影響で兵庫県の寺院に被害がでた為、急遽支援活動を致しました。本堂裏の山からの土砂崩れで、境内は殆ど土砂まみれです。多くの僧侶が力を合わせて本堂の中の土砂を外へとかき出しました。お位牌や教本も土の中から大事に掘り起こしました。
まだまだ復興には時間がかかりそうです。一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。合掌。