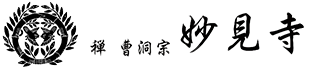-
安閑無事
2019年07月01日
七月になりました、皆さまいかがお過ごしでしょうか?
妙見寺では綺麗なアジサイが咲き、草花がとても生き生きとしております。
禅語の中に「安閑無事(あんかんぶじ)」という言葉があります。
これは言葉の通り、安らかで静かな状態を意味します。
皆さんの人生に安らかな時間はありますか?ただただ日常の仕事や学校に追われる日々を過ごしていませんか?
安らかでないという状態はあれこれ考えている状態です。あれしたい、これしたい、〇〇さんに電話しなきゃ。何時までに起きないと仕事に遅れる、など。頭の中でいつもこのような想いが飛び交っていては落ち着いたとは到底いえないでしょう。
安らかな状態というのは難しいことをするわけではありません。テレビを消して、食べ物を味わいながらよく噛んで食べる。呼吸に意識を向け三回深呼吸をしてみる。
それだけでも日常に安らかで静かな状態が訪れます。
人生を楽しむために様々なことに挑戦することはとても大切です。その中でいつも心が「安閑無事」であったなら、皆さまの人生はより素敵なものになるのではないでしょうか。合掌


-
地蔵様
2019年06月01日
一年の半分が過ぎましたね。皆様いかがお過ごしでしょうか。
私(副住職)の赴任しておりますハワイのお寺では檀家様が毎週土曜日に掃除にこられます。先日はお地蔵さまに手作りの花柄の帽子とよだれかけつけてくださいました。素敵な赤色でとってもお地蔵さまが喜んでおられます。素敵な6月をお過ごしください。合掌。

-
我逢人
2019年05月01日
5月になりました。妙見寺の花々はとても綺麗に咲いております。令和元年、皆様が素晴らしい一年を過ごされますこと心よりお祈り申し上げます。
禅語に「我逢人(がほうじん)」という言葉があります。この言葉の意味は「人との出会いはとても尊いものである」という意味です。
この言葉は道元禅師がお悟りを開くきっかけとなった如浄禅師様との出会いを通して使われたお言葉です。道元禅師は一人では真理を理解することができませんでした。如浄禅師との出会いによってはじめて道元は自分の長年の答えを解決することができたのです。出会いによって人は新しい価値観を学ぶことができます。出会いによって人は新しい道を切り開くことができます。私たち一人一人にも多くの出会いがあるはずです。
常に身の回りの人たちに感謝をし、新しい出会い一つ一つを大切にして毎日を過ごしてまいりましょう。合掌





-
掃除
2019年04月01日
4月になりました。本日新元号が令和に決まりました。明るく平和な日々が続きますことを切に願います。
さて、今月は掃除についてお話をしたいと思います。皆さんは普段どのくらいの頻度で掃除をされていますでしょうか?
掃除が苦手だという人もいらっしゃるかと思います。掃除は仏教においてとても大切な修行の一つです。お釈迦様の時代にも一生懸命掃除を心がけ、お悟りを開かれたお釈迦様のお弟子様がいました。今月はそのお弟子様のお話をしたいと思います。
昔々、インドに「パンタカ」と呼ばれる青年がいました。
パンタカはとても物忘れが激しく、時々自分の名前さえも忘れてしまうこともありました。
そんなパンタカは仏様にあこがれ、仏様の弟子となりました。パンタカは頭の悪かったので、仏様は短い言葉から彼に教えます。
しかし、彼はそれさえも覚えることができませんでした。何年も何年も修行をするものの、パンタカは仏様の教えの一つも覚えることができませんでした。
ついにそれを見かねたパンタカの兄は、ある日パンタカに故郷に帰るように諭しました。パンタカは気を落とし、自分はどうしてこうも頭が悪いのだろう、と門の前で泣いておりました。
するとそこに仏様が通りかかります。仏様は「何故、泣いているのだ?」パンタカに尋ねました。
パンタカはこう言いました。「私は、何故こうも愚かなのでしょうか?あなたの弟子になる資格がありません」
すると、仏様は、「自分を愚かだと思う者は愚かではない。自分の愚かさに目を向けず、自分が賢いと思い上がっているものが愚かなのだ。自分の愚かさを知っている者が真の知恵者だ」と答えます。
そして仏様はパンタカに尋ねます。「お前が一番好きなことは何なのだ?」
パンタカは答えました、「私は掃除が好きです」仏様は、「そうか、お前は多くの事を覚えられないようだから、これからは好きな掃除をしながら、この言葉を唱えなさい」
そう言うと仏様は、ほうきを手渡し、次の言葉を教えました。『塵を払い、垢を除かん』
パンタカは、それなら自分にもできそうだと、喜びます。そして、掃除がはじまりました。『塵を払い、垢を除かん』『塵を払い、垢を除かん』『塵を払い、垢を除かん』。
パンタカはこの短い言葉でさえ忘れてしまいそうになりましたが、何度も何度も繰り返して、やっと覚えることができたのです。そして、数年が経ちパンタカは、仏様に聞きます。
「どうでしょうか仏様、お寺は綺麗になりましたか?」仏様の返事は 「まだまだ完ぺきとは程遠いですね。」
パンタカは何度も何度も掃除を繰り返しますが、どんなに綺麗にしても、「まだまだ」と言われます…
しかし、パンタカは、めげることなく掃除を続けます。パンタカは、ひたすら掃除をして、気づけば20年も経っていました。
ある時、せっかく綺麗にした場所を、子どもたちが来て汚してしまいました。
パンタカは、思わず子どもたちに怒鳴りました。「コラ!せっかく僕が掃除したのに!」その時、パンタカは、本当に汚れている所に気づいたのです。
私は私自身の心の汚れを綺麗にすることができていなかった。
綺麗にしても、すぐに汚れてしまうのは、物も心も同じなのです。
そして、チリや垢は、自分の思ってもいないところにあるのだ、と気づきます。
こうして、パンタカは、阿羅漢(アラカン)の境地に達したのです。
阿羅漢とは、修行して心の汚れを落とし、悟りの第一段階に達することです。
仏様は、皆の前でこう教えました。「悟りを開くということは、沢山のことを覚えることではない。僅かなことでも根気よく徹底してやることなのだ。パンタカは、掃除を徹底してやることでこのように悟りを開いたのだ」こうして、パンタカは、十六羅漢の一人となったのです。おしまい皆さんこの話を聞いてどう感じましたか?パンタカの一生懸命な努力にとても感動しますね
このお話を通して、私たちは2つのことを学ぶことができます。1つ目は「自分の愚かさを知っている者が真の知恵者」であるということです。
私たち人間はいつも自分が正しいと思い、思い上がる傾向があります。
自分が賢いと思って思い上がっている人は、愚かな行為をしてしまったとしても、気づかなかったり、自分は正しいと信じ込んでしまいます。「謙虚」な気持ちを大切にして、自分はまだ成長段階にいるのだと思うことが大切なのです。パンタカのように自分の行いに注意し、いつも反省できる人になりましょう。 2つ目は、「一つの目標を叶えるには根気が必要」だということ。
お話の中で、仏様は皆の前で言いました。
「悟りを開くということは、沢山のことを覚えることではない。僅かなことでも根気よく徹底してやることなのだ。パンタカは、掃除を徹底してやることで、このように悟りを開いたのだ」
今の私たち人間の社会には情報が溢れ、やりたいことが満載です。私もいろいろな事に手をつけてしまうことがあります。好奇心が強いのは良いことではあります。気分転換や、趣味の範囲でいろいろと体験することも良いことなので、けれども、自分の叶えたい大きな目標があるなら、そのことに関しては徹底してやり通す根気が必要になります。あれこれやっていては何も目標を叶えることのできぬまま人生が終わってしまうかも知れません。パンタカは自分の好きな掃除を徹底的に行ったからお悟りを開くことができました。皆さんもとことん自分の目標に対して一生懸命うちこむことのできる人になりましょう。合掌。 -
眼施
2019年03月01日
3月になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。
3月はお彼岸の時期です。お彼岸にはご先祖様のお墓へ行き、亡くなった故人様の幸せを願います。そして自分も苦しみのない仏様の世界である「彼岸」にいけますようにとお祈りをし、お釈迦様の説かれた教えを実践する大切な期間でもあるのです。
今月は「眼施(がんせ)」についてお話させていただきます。この教えは「無財の七施」というお釈迦様の教えで、ものやお金が無くても誰でも簡単にできる7つの布施の一つです。眼施とは、いつも優しい眼差しで人に接しましょうという教えです。
皆さんは普段どんな目をして、人とお話をしますか?ちゃんと相手の目をみて話ができていますか?日本では「目は心の窓」と例えられます。目を見るだけで、自分の気持ちや相手の気持ちがわかってしまうのです。それほど目の動きは大切なのです。目の前の人が悲しんでいれば、優しく安心を与えることのできる思いやりのまなざしを届けましょう。目の前の人が悩んでいたら、一緒にその悩みを親身になって考える思いやりのまなざしを届けましょう。そのまなざしには人の心に愛情を届ける力が宿ります。
最近はスマートフォンでのコミュニケーションが増え、実際に目と目と合わせて会話をする機会が減り、孤独を感じる人が多くなってきているのではないでしょうか。「眼施」はどんな時代においても実践すべき大切な教えなのです。春のお彼岸には特に「眼施」の実践をしてみてはいかがでしょうか。合掌。