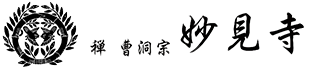-
布施
2018年03月01日
3月になり、春も近づき梅の花が咲き始めました。皆様いかがお過ごしでしょうか?
今月はお彼岸の月です。皆さんはどうお彼岸を迎えられますでしょうか。
「お彼岸」とは私たちのご先祖様がいらっしゃる、苦しみのない仏様の世界のことを意味します。お彼岸期間中は仏様の世界に行けるよう六波羅蜜(ろくはらみつ)と言われる6つの修行を実践する期間だと言われています。今回はその一つである「布施(ふせ)」についてお話をしたいと思います。
皆さんは布施と聞くと、僧侶に渡すお金のことをイメージされるかもしれません。布施とはサンスクリット語で「檀那(旦那)(ダーナ)」といい、他人に財物などを施したり、相手の利益になるよう教えを説くことなど、「与えること」を意味します。
布施の起源は、インドのある僧侶が貧しい家の方に説法をして、そのお返しにあげる者がなく、赤ちゃんのおしめに使っている布をほどこしたのが布施の起源だと言われております。今私がこのウェブサイトを通して皆さんに布施についてお話を書いているのも、その修行の一つです。さまざまな布施の方法がありますが、私たちはこれをどのような気持ちで人に与えるかということを私たちは考えていかなければなりません。
お釈迦様の頃にこんなお話があります。ある日お釈迦様の弟子である舎利弗が信者様からごちそうをいただきました。布施の心を学んでいた舎利弗は、それを尊敬するお釈迦様の所へ持って行き、召し上がってもらおう考えました。舎利弗はお釈迦様の所へ行き、こう言いました。「どうぞ召し上がってください。」お釈迦様は感謝しそれを受け取ると、なぜか自分で頂くのではなく、それを隣の犬へあげてしまいました。それを見た舎利弗は驚きます。そしてお釈迦様は舎利弗に言いました。「そなたが私に供養したのと、私が犬に与えたのと、どちらが功徳があるか?」と。その時舎利弗は気づき、反省をしたという話です。
皆さんはこの話を聞いてどう思いますか?私は最初この話を呼んだ時、もし私が舎利弗ならせっかくあげたものを犬なんかにあげて、と怒るかもしれません。この話で何を伝えたいかと申しますと、与えたものに執着をしないということです。
お釈迦様も道元も、「布施とは、執着しないこと」といいました。
今回の話はちょっと意地悪な行為のように思えますが、お釈迦様は舎利弗に執着しないことの大切さを伝えたかったのです。私たちは時々、自分の都合の良い人だったり、見返りを求めて人にものを与えたりすることがあります。それが習慣になると、その行為は布施ではなく自分の欲を充たすための執着になってしまうのです。
ただ他人の幸せを願い、どんな人であっても愛する気持ちをもって布施をすることがお釈迦様、道元のいう執着しないという大切な禅の教えなのです。布施の教えをお彼岸の期間、また日常生活で実践していきましょう。合掌。